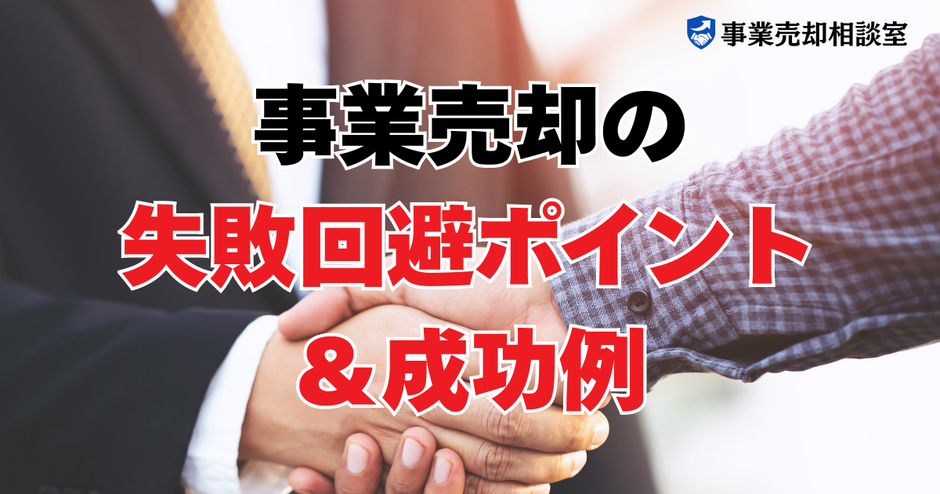
事業売却はなぜ失敗しやすいのか?
事業売却は会社経営における大きな意思決定のひとつです。撤退・再編・資金確保・後継者問題の解決など目的はさまざまですが、実際には多くの経営者が「売却の壁」に直面します。
なぜなら、事業売却は専門的で複雑なプロセスを経る必要があるからです。買い手探し、条件交渉、デューデリジェンス、契約書締結…。それぞれの過程でリスクが潜んでおり、準備不足のまま進めてしまうと「価格が下がる」「買い手が見つからない」「契約破談」などの失敗に繋がります。
本記事では、事業売却でよくある失敗例と、それを防ぐための注意点を整理した上で、実際の成功事例を5つご紹介します。そして最後に、従来のM&Aの課題を解決できる「事業売却相談室」という新しい選択肢もご案内します。
事業売却でよくある失敗例
1. 売却価格が想定より大幅に低くなったケース
「もっと高く売れると思っていたのに…」というのは典型的な失敗例です。 財務状況や契約内容、将来の収益性などを正しく整理せずに交渉を進めると、買い手側の評価が低くなり、想定より大幅に安い金額での売却を余儀なくされます。
2. 買い手が見つからず売却に至らなかったケース
買い手探しには時間と労力がかかります。仲介会社のネットワークに依存してしまうと、自社に合った買い手が見つからず、数か月〜1年以上経っても売却が成立しないケースも少なくありません。
3. 従業員・取引先への説明不足によるトラブル
売却の情報が社内外に広がると、不安を感じた従業員の離職や、取引先からの信用低下に繋がることがあります。特に説明を怠った場合には「なぜ突然…?」と不信感を招き、事業継続に支障が出る可能性もあります。
4. デューデリジェンスで問題が発覚して破談に
買い手によるデューデリジェンスで、未整理の契約書や過去の税務リスク、労務問題が発覚すると、交渉が破談になることがあります。書類の不備やリスクの隠蔽は失敗の大きな原因です。
5. 契約条件を十分に確認せず不利な契約を結んだケース
契約書には「表明保証」「競業避止義務」など、売り手にとって負担になる条項が盛り込まれることがあります。弁護士の確認を怠ると、売却後に予期せぬトラブルや損害賠償責任を負うリスクもあります。
事業売却で失敗しないための注意点
では、失敗を避けるにはどうすればよいのでしょうか。ポイントを整理します。
✅売却目的を明確にする
「撤退」「資金確保」「後継者対策」など、目的がはっきりすれば売却方法の選択肢も絞れます。
✅事業価値を正しく把握する
財務データに加え、ブランド力・顧客基盤・知的財産などの無形資産も含めて評価しましょう。
✅専門家を活用する
仲介会社・会計士・弁護士の知識は不可欠。複数の専門家を比較し、自社に合った支援を選びましょう。
✅買い手との交渉は丁寧に
焦って交渉を進めると条件面で不利になります。買い手のニーズを理解し、双方が納得できる着地点を探すことが重要です。
✅従業員・取引先への説明を怠らない
信頼関係を守るためには、適切なタイミングで丁寧に情報を共有することが不可欠です。
✅契約書の確認を徹底する
特に表明保証や競業避止義務などは、売り手に過度な負担を課すケースがあるため、必ず弁護士にチェックしてもらいましょう。
成功事例5選
ここでは、実際に事業売却を成功させた事例をご紹介します。
1. 赤字店舗を早期売却し、本業に集中できたケース
飲食チェーンを展開していたA社は、一部店舗が赤字続きで経営を圧迫していました。不要な店舗のみを売却し、本業である郊外型店舗に集中することで収益改善を実現しました。
2. 後継者問題を解決し、従業員の雇用を守れたケース
製造業を営むB社は後継者不在に悩んでいました。業界内の大手企業に事業を譲渡することで、従業員の雇用を守りつつ、会社の歴史を次世代に繋ぐことに成功しました。
3. ECサイト事業を売却し、新規事業の資金に充てたケース
スタートアップのC社は、伸び悩んでいたECサイトを売却。その資金をAI事業に投入し、事業の大転換に成功しました。
4. 飲食店を事業譲渡し、オーナーが第二のキャリアへ進んだケース
個人経営の飲食店オーナーD氏は、健康上の理由から事業継続が困難に。事業を売却することで引退資金を確保し、第二の人生を歩み始めました。
5. 地域サービス事業を大手企業に売却し、規模拡大が実現したケース
地域密着型サービスを展開していたE社は、大手企業に事業を売却。その後、大手の資本力を活かしてサービスが全国展開され、従業員や利用者にとってもメリットの大きい結果となりました。
従来型M&Aの課題
ここまで一般的な事業売却の流れを説明しましたが、実際の仲介型M&Aには大きな課題があります。
✔️期間が長い:買い手探索〜クロージングまで数か月〜1年以上かかる
✔️費用リスクが高い:着手金・月額報酬・中間金などを支払う必要があり、売却不成立でも数百万円が無駄になる
✔️交渉が複雑化する:株式譲渡が主流で、経営権や雇用、債務まで引き継ぐ必要があり条件調整が難航しやすい
このため「売りたいけど、時間やコストが負担で諦める」という経営者も少なくありません。
事業売却相談室という新しい選択肢
こうした課題を解決するのが「事業売却相談室」です。
特徴1:スピード売却が可能
「自社での一次買取」や「既存ネットワークへの即時マッチング」により、最短で数日〜数週間での売却・現金化が可能です。
特徴2:費用リスクがない
仲介型のような着手金・月額報酬・中間金が不要。売却が成立しなければ費用が発生しない仕組みです。
特徴3:部分的な事業売却に対応
会社全体ではなく、ECサイトや飲食店舗など「一部事業だけ」を売却できます。本体は残して不要な事業だけを整理できるのが大きなメリットです。
特徴4:スピーディかつ透明性の高い取引
査定から契約・現金化までを一気通貫で行うため、従来型M&Aのような不透明さや長期化リスクを避けられます。
💡まとめ:失敗しない事業売却を実現するために
事業売却は失敗例も多く、正しい準備と専門家の支援が欠かせません。 しかし、従来型の仲介M&Aには「時間」「コスト」「不確実性」といった課題がつきまといます。
「事業売却相談室」なら、そうしたリスクを避けつつ、スピーディで確実な売却を実現できます。ぜひお気軽にご相談ください。

